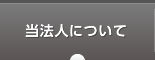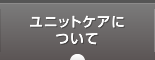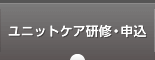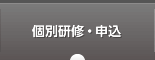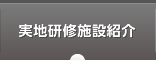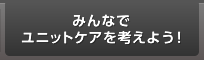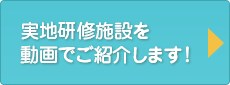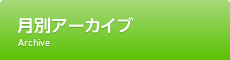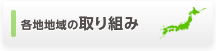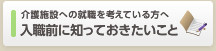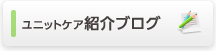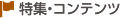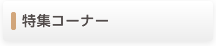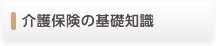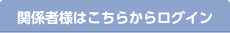この頃の新規施設
2013年7月2日 更新
管理者研修やリーダー研修では、各施設の建物や運営の状況がよくわかる。
この頃はユニットケアが発足した当時、建物はどう建てたらいいか、運営はどうするかと悩んでいた頃に戻ってしまった気がする。建物は「ガイドライン」があり、運営についても国の基準が明確になっているし、研修や本もあるのだが、情報が行き届いていない感がある。この2~3年は、小規模施設がどんどん誕生しているが、その小規模の方に課題が多い。
今もユニットリーダー研修の最中である。
*「人手がないので2ユニットを一緒にケアしている」
→ そもそも、固定配置の必要性を分かっているのだろうか?これでは従来型施設と何ら変わらない。報酬だけ多くもらい、今までと同じ運営をしていたら、それは従来型施設に申し訳ないのではないか?
*「人手がないので、夜勤者が早番の仕事と遅番の仕事をカバーしている」
→ エー、何回夜勤しているの?16時間夜勤を9回している。エー、そうなると昼間の勤務は3~4日。入居者が起きている日中に関われるのは、30日中3日しかない。これでは入居者の事はわかるまい。こなす介護の悪循環が存在する。介護者の離職率も高いだろうし、専門家としての教育も出来ないだろう。
そこでわいてくる疑問。
「これでよく認可されたね・・・?」
経験から言うと、新施設の認可には、理念、建物の図面(理念に基づいた図面)、理念に基づいた運営方針、職員配置やシフト、経営のシュミレーション(職員の給与や償還計画)・・・の提出が有り、確認をされているはずだが・・・。
研修では、老人福祉法の33条を知らない人が多い。
従い、上記のような運営が多く存在してしまう。
えー!運営基準の老人福祉法33条を理解していなくとも認可される・・・?
それはないでしょう・・・。
認可申請前の研修(事業者・建築家・行政)の必要性を感じる。取りかかりに差異が生じていると、運営が始まってからの修正はなかなか難しい。
ちなみに、栃木県は市町村担当者の研修を数年前より単独開催している。我がセンターの図面分析では、ガイドラインより外れた建物がないのは、栃木県だけである。(秋葉)