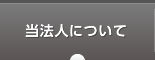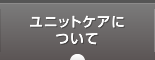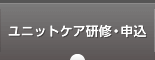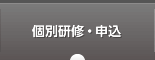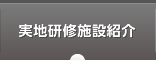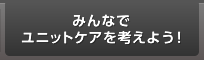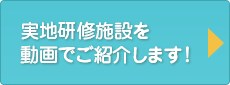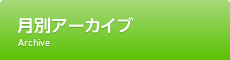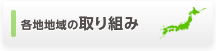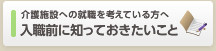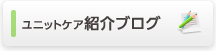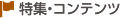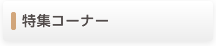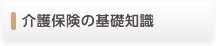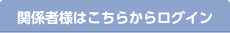理念の実現へ(菜の花館 ユニットリーダー)
2025年6月18日 更新
特別養護老人ホーム菜の花館のユニットリーダー兼実習受入担当の星野です。菜の花館では「その人らしく、いきいきと」といった理念を掲げています。しかし、リスクを考慮した考えと、業務を優先したケアを行っており、ユニットケアの実践からは遠ざかっていました。このままでいいのか?という疑問と「その人らしく、いきいきと」といった理念の実現に向け改めなければいけないのではないかと強く感じていた頃、施設長から「ユニットリーダー研修実地研修施設を目指す」という宣言を受けました。
チャレンジすると言われたものの分からないことが多く戸惑いました。センターの短期集中サポート研修で、設えなどをはじめとしたハード・ソフト面において指導を受け、また自分自身も5年前にユニットリーダー研修を受講した際に感じていた熱量や「こうしたい!」といった想いが再燃し、ユニットケアの概念・仕組み・考え方を再度指導して頂く中で、具体的にどのようにアクションを起こせばいいかビジョンが見えてきました。
食事面では温冷配膳車を中止にし、ユニットでの炊飯になり、夜勤体制も16時間から8時間夜勤に変更になったり大きな変化がありました。職員の意見も賛否両論ある中、施設全体での取り組みでした。
結果として無事に今年度合格することができましたがここからがスタートです。ユニットケアは日々続けていくことが重要であり、今回の取り組みにあたり、トライアンドエラーの精神で新しいアイディアを出し、日々挑戦することの大切さを学びました。「その人らしくいきいきと」といった理念の実現の為にご入居者から「ここにいてよかった」そう言ってもらえるようなユニットを目指します。そのためにも「楽しむ」ことを忘れずにユニットリーダーとして周りを巻き込みながらユニットケアの本質からぶれることなく頑張っています。
そんな楽しむ姿やこだわりあるユニットをお見せできたらと思います。
実習生の皆さんお待ちしています。
「自分が入りたい施設」を目指して(泊村 むつみ荘 主任介護員)
2025年5月15日 更新
北海道古宇郡泊村にある泊村特別養護老人ホームむつみ荘で主任介護員をしています外村です。むつみ荘では入居者へ「入居前の暮らしの継続とその人らしい生活をしていただくこと」を大切にしていますが、正直時間に追われ職員都合での声掛けや入居者にゆっくり関わる事が出来ない事が多々ありました。施設の建物は綺麗で立派、個室でプライベート空間はしっかりしているが、『このままで入居者は「ここに来てよかった」と思ってくれているのか?』と考えていたところ、実地研修施設募集の案内があり、初心に戻り今一度ユニットケアを理解する勉強の場だと思い、取り組みました。
手厚い短期集中サポートを受けさせていただき、まずは入居者一人ひとりを知る事と24シートの見直しに取り掛かりました。ケアプランとの照合性や聞き取りシートの活用、排尿データをとる事から始めた結果、紙パンツを使用していた入居者が布パンツに変更することができました。何より家族から「こんな日が来るとは思わなかった」と笑顔で話された事は印象深く心に残っています。また、なじみの家具の持ち込みや入居者の様子や家族が心配している事を一緒に考え、以前より家族と共有する場面が増えたように感じるようになりました。リビングの設えに関しては各ユニットリーダーが中心となって家具や観葉植物を増やすなど初歩的な事から考え直し準備しました。
全てが一から学ぼうと必死で、リーダーからユニットケアについて取り掛かっている事や協力してほしい事をユニット職員に上手く伝えられず事後報告が多々あった事は反省しなければなりません。何事もリーダーだけでなくユニット職員も一緒に考えながら取り組む事でいろいろな視点から考える事とチームワークの大切さにも改めて気付きました。
困っている時や迷っている時は施設長はじめ多職種にも相談し入居者に寄り添うことを一番に考え、その人らしい生活(暮らし)を考えています。実地研修施設となりたくさんの出逢いがあると思います。私達の施設は皆さんからのご意見やご指摘を受けながら成長していきたいと思っております。泊村は小さな漁村ですが、海がとても綺麗で釣り人もたくさん来られ入居者の皆さんは魚を骨だけきれいに残し食べられます。ぜひ見ていただきたいです。最後に施設長がいつも話されている「自分が入りたい施設」を目標に職員一丸となって入居者と家族の幸せの為に日々努力し実地研修施設として成長していきたいと思っております。
開設から10年の歩み (ラ・ポール有田 介護長)
2025年5月15日 更新
ラ・ポール有田、受け入れ担当の馬込です。
私は平成27年の開設時、オープニングスタッフとして勤務を開始しました。開設前から2か月という研修期間があり、かつユニットリーダー研修も就業開始前から受講させて頂けるという、今考えると恵まれた環境だったなと思い出されます。開設時研修でも「本気でユニットケアに取り組む」と当時から宣言されており、開設して初年度の事業計画で、施設長は「夢を叶える介護をする」「地域で1番の施設になる」「5年でユニットケアの実地研修施設となる」の目標を掲げられました。
当時の私は開設時のユニットリーダーに任命を受けた事もあり、また、リーダー研修を受講させてもらい、やる気に満ち溢れ、スタートしました。やる気十分の私は、1年目、限られた予算の中で、ユニットの家具を購入し、家庭的な雰囲気をつくることにこだわりました。また入居者さんの夢を叶えるべく一緒に映画館に行ったり、自宅に帰ったり、野球観戦に行ったり、一緒に乗馬をしたこともありました。そんな全力疾走の1年目、はやくも2年目で息切れをします。開設時の施設あるあるなのですが、退職をする職員が続き、ユニットケアを実践する事がままならない時期もありました。それでも歩みは止めず、少しずつ形を作っていきました。
語りつくせないほど紆余曲折ありましたが、10年目、実地研修施設の仲間入りができ、いまでは、入居者一人ひとりのペースに沿った暮らしができる施設に近づいているのではないかと感じています。これからも「ケアやユニットのシステムが職員都合になっていないか」自問自答しながら、10名のユニットリーダーと一緒に「その人らしい暮らし」を追求していきたいと思います。