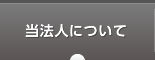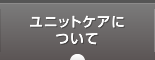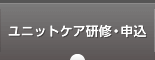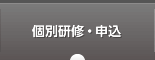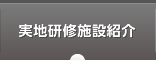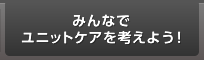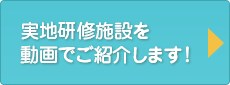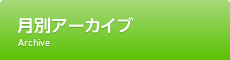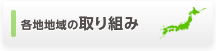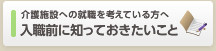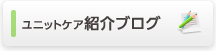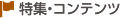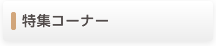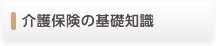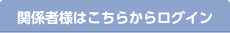「相談員として」(特別養護老人ホーム灯光園 髙塚 祐美)
2020年4月1日 更新
私は相談員として、お年寄りの入居の際のお手伝いをしています。それまで長く住んだ自宅からの引っ越しです。
ユニットケアでは「暮らしの継続」が合い言葉です。施設でも家での暮らしを続けられるとはどういうことなのでしょうか?それは、家と同じような形態で暮らすということではなく、自分が自分らしくいること、障害や不便なことがあっても変わらず自分であり続けることです。
多くの人が毎日何らかのこだわりをもって暮らしています。朝は日の出と共に起きる習慣の方、夜のテレビを観て10時過ぎに休まれる方、食後は必ずコーヒーを飲みたい方、自分の時間を自分のペースで過ごします。そういう生活を灯光園に入居をしても続けていただきたいと思います。
灯光園では入居の準備の際にご家族に「引っ越しをする」という気持ちで準備をお願いします。今まで使っていた箪笥や鏡台、テーブルや椅子を持ってきていただきます。また、家族や思い出の写真を飾って、安心して過ごせる部屋にしましょう、と話をさせていただきます。環境が変わっても自分の部屋の居心地の良さは変わらないようにしたいと思います。時には、自宅におじゃまをさせていただき、その方の今までの人生を感じて、部屋の雰囲気を再現できるようにと思います。
入居者のこだわりや役割が失われずに、その人を個としてとらえ支えること、その時間を一緒に共有できることを嬉しいと感じます。
「灯光園の暮らし」(特別養護老人ホーム灯光園 羽田 美由紀)
2020年4月1日 更新
リーダー研修では、老人福祉法に基づく「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第33条」が繰り返し話されます。
「入居前の居宅における生活と入居後の暮らしが連続したものとなるように配慮しながら自律的な日常生活を営むことを支援」することが大切なところです。初めは具体的にどうしたらいいのかわかりませんでした。研修の中で、先進施設の講師の方が具体的に「うちではこんなふうにしています。起きたい時に起き、朝食を食べる。買い物へ行きたい時は出来るだけ工夫して出かける。好きなおかずは多めによそってもいい…」と自施設の事例を話してくれました。また実地研修でも、座学の通りのことが行われているのを目の当たりにしました。
偏食で食事の好みが給食では追いつかないFさんはおかずを購入し、ユニットで煮炊きもします。以前は考えられないことですが、今は男性職員もチーズ入りの卵焼きを作ります。職員も慣れてきました。左麻痺があり、車いす自走のMさんは目が覚めるとコールで職員を呼び、身支度を整え、車椅子に移ります。車いすに座った時から自由な生活を送ります。「朝ごはんを食べようかな」「ちょっと散歩に行ってくるよ」と、自分のペースで生活しています。Sさんは生活の殆どに介護が必要です。目が覚めるまではカーテンを開けません。一斉介護をしていた頃はできなかったことですが、職員の意識が変わり、当たり前になりました。
少しずつ、研修で具体的に教えていただいたユニットケアに近づいてきたな、これが自律的な生活の支援なのかな、と感じています。
「ユニットケア研修の魅力」 (特別養護老人ホーム 岩出憩い園 前田 美智子)
2020年3月2日 更新
フロアーリーダー 前田 美智子 (社会福祉法人 紀の国福樹会 特別養護老人ホーム 岩出憩い園)
平成24年、開設前の研修で初めてユニットケアを知りました。「一人ひとりの生活リズムやライフスタイルに合わせたケア」であると知り、是非やってみたいと思いました。開設後は、なかなかユニットケアは浸透せず、ケアの統一も図れませんでした。
離職していく職員が多く、従来型の勤務経験のある職員とは意見がぶつかり、私もだんだんと「ユニットケアではなくても、良い介護をすれば良いのでは・・・」と思うようになりました。そんな時、リーダー研修を受講させていただく機会に恵まれました。介護現場で働いておられる講師は知識と経験から事例を交え具体的なアドバイスや実践方法を教えて下さり、知識を得ることが出来ました。
グループワークでは、他施設の状況や課題等について意見交換を行い、悩みを抱えながらそれぞれの場所で頑張っている仲間がいることを知り、私も頑張らなければと新たな思いで実習に臨むことが出来ました。実地研修では、暮らしの場を学ぶ貴重な体験をさせていただきました。キッチンで調理を行っていた入居者が「これどうぞ。食べてみて」とお裾分けして下さったことに感激しました。出前を頼んだり、ユニットを超え入居者同士が声を掛け合い、クラブ活動や買い物に行かれる姿はご近所付き合いのように感じました。
入居者の生き生きとした表情や自律した暮らしぶりを見て「この光景を施設に帰って皆に伝えたい。施設を暮らしの場に変えたい」と思いました。
研修から4年後、岩出憩い園は実地研修施設になることが出来ました。研修に来られる皆さんに施設を暮らしの場に変えたいと思っていただけるよう、これからも仲間と共に頑張ります。