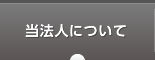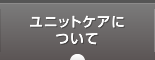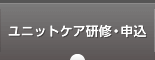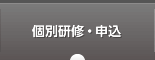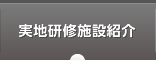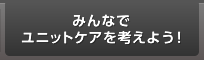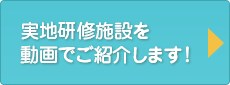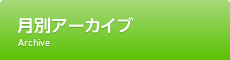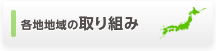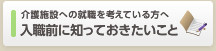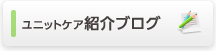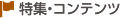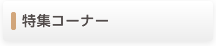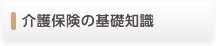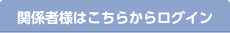「ユニットケア研修での学び~広がり~」(シルバータウン相模原特別養護老人ホーム 丹治 昌子)
2018年10月1日 更新
研修を受ける前はユニットケア=少人数体制の個室だと思っていました。
ケア内容も振り返ると従来型の一斉一律の業務優先、職員目線、職員主体のケアを行っており、それが当たり前でした。
この研修を受講し、入居者の「暮らしの継続」、1日24時間の暮らしの積み重ねを支えることがユニットケアの理念、基本ということを学びました。研修を受講したリーダーを中心に本格的にユニットケアに取り組み実地研修性の受け入れ施設となる事が出来ました。
今では入居者の行動範囲も広がり、施設全体で入居者の暮らしを支えるという雰囲気ができ始めていると感じています。また従来型多床室等でもユニットケアの取り組みが始まっております。ご本人、ご家族の意向、希望を取り入れ、根拠に基づいた24Hシートの作成や、課題もたくさんありますが、最後までその方らしい暮らしを支えるというのが、ユニットケアの魅力と感じる日々です。
「梅干し作り」(シルバータウン相模原特別養護老人ホーム 中村 太一)
2018年10月1日 更新
ある日突然、入居者から「毎年梅干しを作っていたけど、もうこういうところに入ったから無理ね」と諦めともとれる言葉が聞こえてきました。
ユニットケアの理念は「暮らしの継続」です。私は、この方に「無理なことはないですよ」と1から教えてもらい、必要物品を用意し、一緒に梅干し作りを行いました。その入居者も「もう出来ないと思っていたからうれしいわ」と満面の笑みを浮かべて下さいました。たとえ些細なことであったとしても、その方にとっての当たり前だった暮らしをサポートできたことをうれしく思いました。そして、それを実践できるのが「ユニットケア」だと実感しました。
「暮らしの場の看護師として大切な事」(特別養護老人ホーム桜の郷元気 野末 知美)
2018年10月1日 更新
平成20年に桜の郷元気に就職した頃、私はユニットケアがどういうものなのか理解していませんでした。ゆっくり時間が流れているなぁという印象だったのを覚えています。
今では、個別ケアの大切さを理解し、入居者個人のペースで日常が送れるよう、医療面でのサポートをしています。
ユニットでは、介護職員を固定配置して個別ケアを行っていますが、看護師は一人一人が全入居者の状態を把握し健康管理をしているため、情報量も多く、関わりが浅くなってしまっていると感じることがありました。今年度より、健康管理も個別ケアができるよう看護師のユニット固定配置を開始しました。今までよりも、入居者との関わりが増え、みえてなかった所もみえるようになりました。これからも、入居者それぞれに合わせた医療面でのサポートを介護職と共に行っていきます。