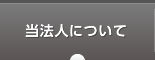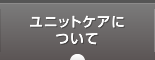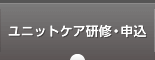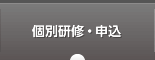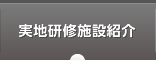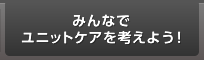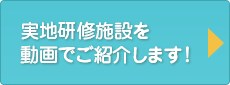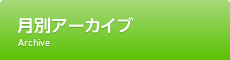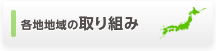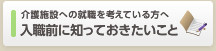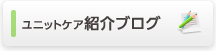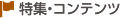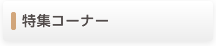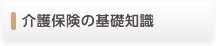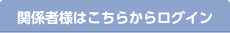現場との情報連携について(特別養護老人ホームかわいの家 関 勝之)
2023年3月1日 更新![]()
私が施設長を拝命して早3年経過し、施設長就任時に感じていたこととして、課題の集約と問題解決策において、より迅速にできる方法がないかという事です。
当時ユニットリーダーやケアマネージャー、看護職員など個々での連携は取れているが、管理職への相談が遅く、結果、改善が遅れるという悪循環が垣間見られました。
その状況を打破すべく、思いついた方法としては各課、各ユニット会議に多職種が参加し、第三者視点で問題と感じたことを皆で共有しあうという仕組みの運用でした。
運用方法としては、各会議の日程を事前に決め、その情報を共有し多職種の参加調整を行う。参加者は、各ミーティングでの議題の中から施設での検討課題を抽出しメールで共有。その後改善につなげるという流れの運用を開始。このことで、担当職員が抱え込まず、多職種での連携に繋がり、改善スピードが上がるという結果に繋がっています。また、私自身もこの多職種参加によるミーティングの時間を、理念の浸透につなげる機会として位置づける事で全職員に再度説明する機会にもなりました。
コロナ禍になり、感染状況によってはミーティングが開催できない月もあったが継続して行ってきたことで多職種連携がより強化されたと実感しています。この他職種ミーティングが行えているのもコロナ過に於いてユニットケアに尽力し、ご入居者の変化や施設内の課題に気付き意見をしてくれる全職員の力だと感じております。
新型コロナウイルスの収束を願って(特別養護老人ホーム花巻あすかの杜 中村 光一)
2022年12月1日 更新![]()
私は、当施設に昨年度入社で、今年度から施設長に就任しました。良いこと悪いことも含めて、色々な事案があり、喜んだり、悲しんだり、悔んだりもしています。
ご承知のとおり、新型コロナウイルスの関係もあってユニットリーダー研修実施研修受入は2年半も無かったため、どの様に進んでいくのか体験していないので正直不安でした。しかも施設長との対話… (受講者の方が介護歴は長いので)と思いながらも色々と情報交換させて貰い自分としては、大変参考になっています。しかしながら、受講者が感染して中止となったり、どこの施設もだと思いますが、いつ感染しないとも限らないのでビクビクしている状況です。
また、入居者とご家族とのコミュニケーションが以前みたいに取れないことが残念です。以前は自由にユニットに入って充分に取って頂いたり、各種行事にご案内していたと聞いていますが、新型コロナウイルスは一向に収まる気配がなく、既に第8波となっています。今まで、感染状況に応じてオンライン、ガラス越し、アクリル板越しと対応してきました。とりあえず、施設の造りが幸いし、ガラス越し面会で対応していますが、やはり触ってお話ししたいのがご家族様の願いだと思います。
まだまだ、色々な事案がありますが、一日でも早く新型コロナウイルスが収束することを祈念しています。
最後に、日頃からユニットケアを頑張って推進している職員の方々に感謝、感謝です。
「自分たちが入りたい施設を創る」(特別養護老人ホーム灯光園 八木 麻里)
2022年10月3日 更新![]()
6月、施設長になって初めてユニットリーダー研修実地研修生を受け入れました。施設長、受け入れ担当者も替わり、何もかもが初めてなので、できていること・できていないことを確認できる絶好の機会です。「来ていただいて、本当にありがとうございます!」職員や理事の方々にも、「来てくれるよ!」興奮して報告しました。
ユニットケアには暮らしの継続という理念があります。これから取り組む実習生さん達は、「自分の施設と全く違う」と驚いたとのことでしたが、ユニットケアしか経験がない私はそのことに驚きました。灯光園は平成13年から移転を機にユニットケアを勉強し始めています。みんなで話し合いながら一歩一歩進めていった記録が残されており、当時の職員達の思いが詰まっている分厚いファイルは3冊にもなりました。実地研修施設となった時に、「ユニットケアに思う」という職員の一文があります。
『・・・そして、「施設」のイメージが変わった。介護保険が始まり、入居する施設を自由に選ぶ時代。もしも介護が必要な身になったら・・・真っ先に思うのは、「子供たちに迷惑をかけたくない」ということだ。施設に入居させてもらって、他人様にお世話になる(お金で割り切れる)生活の方がいっそ気楽かもしれない。さて、実際にそうなった時、果たして今の灯光園に入りたいと思うだろうか。答えは「YES」だ。朝は、「時間だから」と起こして欲しくない。朝食はパンとコーヒーがあればいい。たまには喫茶店でおいしいコーヒーを飲んだり、レストランでランチもしたい。・・・こんなわがままを聞いてくれそうじゃないですか、灯光園なら。」
どれだけその人の“暮らし”を大事にできるか、私たちが今、創っていかなければならない・・・その重みを感じている。』
あの頃、ユニットケアを創り上げた職員達は、地域で灯光園を見守ってくれています。パート職員として支えてくれている人もいます。私たちは、自分がされて嫌なことは人にもしない、自分が入りたいと思う施設を作る、この志を引き継いでいかなければなりません。