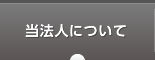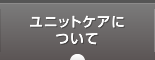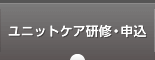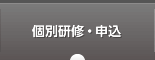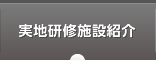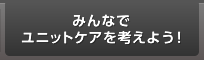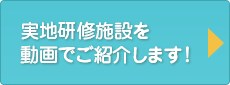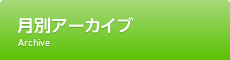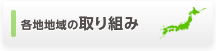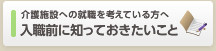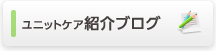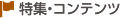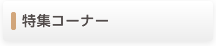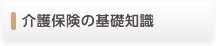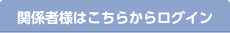「老健のユニットケア・この頃」(介護老人保健施設 ぺあれんと 河嶋哲郎)
2017年11月15日 更新![]()
ユニットケアは個室、個別ケアなので、患者、家族ともに入院と比べて、はるかに自由度が高い。そういう環境なので、家族ともどもわがままいっぱいになる方もでてくる。病気によっては老健では治療できず、入院治療が(標準治療)必要な方もでてくる。ほとんどの方は治療がすんで再入居になるが、中には環境が変わったせいで(わがまま気ままが通らず)せん妄状態となり食事も拒否し、治療どころではなく早々に帰ってくる方も散見される。帰ればせん妄状態は改善され、食事もとれるようになってくる。
最近では最初から入院拒否の方もでてきている。ありがたいのかどうか悩むことが増えてきたこの頃です。
「『ユニットケア』は『認知症ケアの救世主』」(きのこ老人保健施設 宮本憲男)
2017年11月15日 更新![]()
認知症専門の施設である、きのこ老人保健施設は、平成8年に開設し平成12年にはユニット化を行った。それは何故か。「ユニットケア」には認知症の中核症状に対して絶大な効果が認められたからである。
10人程度の「小さな単位」は見当識障害がある方に対して生活上の違和感を感じさせにくい。ユニットへの「職員固定配置」は記憶障害のある方に対して顔なじみによる安心感が得られやすい。そして、入居者一人ひとりのことを十分に理解し、「24Hシート」で共有している職員が寄り添うことにより、判断力の低下した方に対してさりげなくサポートできる。これは、認知症によって出来なくなる不安を取り除くことだけでなく、職員との関係性を深めることにも繋がり、認知症になっても「笑顔」で生きていくことを支えることができるのである。
認知症のある方に対して優しいユニットケアは、認知症のない方に対しても優しい施設になれるのだ。
「自宅でない在宅」(有吉病院 有吉通泰)
2017年11月1日 更新![]()
医療施設であっても自分らしく心地よく過ごしていただけるように、『自宅でない在宅』としてのユニットケアを導入して15年。私自身も歳を重ね、意欲は低下するとばかり思っていましたがとんでもない。歳を重ねるごとに体力が落ちていくことは仕方ないとしても、気力は萎むどころか、高齢者の気持ちが自分のこととしてわかるだけに、もっと、できることがあると思うのです。
先日、私と同じく団塊の世代の患者さまが脳梗塞を発症後、急性期治療を終えユニットケア病棟に入院されました。生活全般に介助が必要ですが、入院して真っ先にでた言葉が「ここは空気がいい。やっと元気になれそう。」。今後の目標はトイレでの自立ができれば自宅に帰ることです。オムツ外しの取り組みが個室化へのきっかけでしたので、こうして前向きにがんばる入居者さまをみると自分のことのように嬉しくなります。まだまだ、私もがんばろう!と。