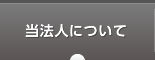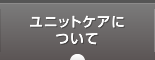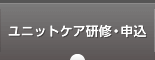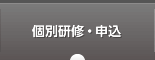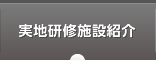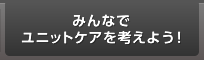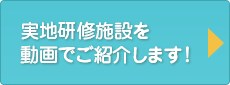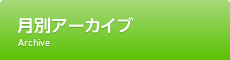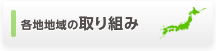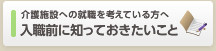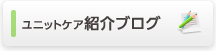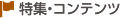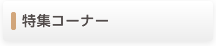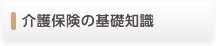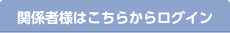「わたしがわたしらしく心地良い居場所」を目指して(特別養護老人ホーム第Ⅱあま恵寿荘 加藤 美由紀)
2024年11月15日 更新![]()
こんにちは。今年度よりユニットリーダー研修実地研修施設となりました、愛知県にある特別養護老人ホーム第Ⅱあま恵寿荘、加藤です。
私事になりますが、地域から施設にギアチェンジして早15年となりました。初めて施設の生活に触れた時、頭の中にはたくさんの「???」がありました。これまで地域の中で暮らしている高齢者の生活について、問題の大なり小なりはあったとしても、それぞれが自分の生き方、暮らし方をしている、それはごく当たり前の日常でした。それが、自宅から施設に移った途端、その人らしい生き方が見失われ、当たり前が当たり前でなくなり、暮らしとは程遠い現状に「???」と共に衝撃もありました。
10年前、法人で初めてユニット型の施設を開設することになった時、ユニット型であれば、「わたしがわたしらしい心地良い居場所」を作ることが出来るのではと思いました。けれど形はユニット型であっても、そこにユニットケアの理解がないとこれまでと何ら変わることのない現状に「???」と共に打ちのめされ、自分の甘さを痛感しました。
それから10年近く・・・どういう経緯でユニットリーダー研修実地研修施設までたどり着いたのかは話せば長~い一つの物語であり、ここで書くには長すぎて足りません。けれど、もしそんな話でもご興味があればぜひ、第Ⅱあま恵寿荘へ実習や遊びに来てください(笑)。
そして、今回、ユニットリーダー研修実地研修施設に指定されるまでに、本当にたくさんの方に支えていただきました。そして同じ方向を見るたくさんの素晴らしい仲間にも恵まれました。みんなにこの場を借りて心から感謝を伝えたいと思います。そしてまだスタートラインに立ったばかりです。これからも懲りずにどうぞ「共に」よろしくお願いします。
暮らす人も支える人も共に敬い
暮らす人も支える人も共に自分らしく
暮らす人も支える人も共に支え合う心地良い居場所
第Ⅱあま恵寿荘は暮らす人も家族も働く人もすべての人が「わたしがわたしらしく心地良い居場所」であることを目指します。


私の中のユニットケアのはじまり ~ミーちゃんの思い出~(介護老人福祉施設IGLナーシングホームシャレー 渡辺 正子)
2024年10月15日 更新![]()
このお話は今から35年前の私が、介護職員として働き始めてから2年目の出来事です。
私の施設に70歳のご婦人が入居されました。
その入居者は、キューピーのお人形にたくさんの布を巻き、胸に抱えてあやすように大事に抱えていらっしゃいました。彼女の視力はほとんどゼロで、彼女の右の眼の前でスタッフが手で大きく字を書くことで、一文字ごとの理解が出来ます。後は身振り手振り、全身を使って意思伝達、意思確認をしていきます。
私から入居者に「だれ?」と書くと、かすかな声で「ミーちゃん」と答えました。彼女はベッドの上でも、中央はミーちゃんに譲り、自分は今にも落ちそうな端で寄り添って休まれています。食事をする時も、まずはミーちゃんの口にパンを運び、その上から牛乳を運び・・・。当然、キューピーのミーちゃんの口では納まらず、床へと流れ落ちていきます。ミーちゃんの食事が終わるとようやく、ゆっくりと彼女の食事が始まります。これが、毎食事時間の光景です。トイレに行く時だって、抱っこして一時も離れることはありません。
そんな彼女は、入居から一週間、一度も入浴が出来ていませんでした。私は、こう呼びかけてみました。
私 「ミーちゃん、汚れてる。かわいそう・・・・・。」
彼女「・・・・・」(ちょっと困った顔)
私 「一緒にお風呂に入れてあげませんか?お手伝いしますよ!」
その結果、身振り手振りと指文字で一緒にお風呂の準備から始めました。タライに湯を張り、バスタオルを広げ、彼女の手を取りゆっくりとタライの中に手を入れてみました。
すると、なんと彼女は、優しい笑顔で優しくミーちゃんの服を脱がされ、入浴を一緒に行うことが出来ました。
さらに、ミーちゃんの入浴が終わると、自ら隅の方で服を脱ぎ始めました。そして、自分で頭を洗い、体を洗い始め・・・、もうここからは言葉はいりませんでした。
とても貴重な経験をさせていただきました。
彼女は障害のあることが理由でしょうか。
出産後直ぐに子どもと引き離されて生活をされていたことを聞き、「一番大切なミーちゃんを私たちスタッフも大切にし、その人の人生に思いを寄せ一緒に生きること」こそ、今も昔も変わらない「良く生きる」事への支援なのでしょう。これからも、ケアの視点は変わらず「尊厳が守られ、自分らしく生きる」ユニットケアそのものだと思います。
現在、私は76歳、施設長ですが、仕事が楽しい、日々進化する介護技術、ユニットケアの視点を学んだこと、実習施設になったことで、まだ、また、ただ知りたい、学びたいことが沢山あります。35年前にこの仕事を選んでよかった、と改めて思っている。いつまで現役で楽しめるのか・・・・。


30秒で分かる、たぶのきの「暮らし」(特別養護老人ホームたぶのき 小林 佳子)
2024年9月13日 更新![]()
「施設」ではなく「家」
※「行ってきます!」「ただいま」の関係
※建物へのこだわりが凄い
「入居者と共に生活する事」を意識しているので、職員の挨拶は、出勤時は
「ただいま」、退勤時は「行ってきます」と入居者に声をかけています。
家庭的で落ち着く「たぶのき」を是非、見に来てください。
「ユニット内キッチン」で「目の前で調理」
※食事の準備、片付けは入居者と。
※ときには店屋物注文も。
「食事」は「美味しく・楽しく」にこだわり、入居者の目の前で調理をします。
出来上がった食事は、職員も入居者と一緒にいただき、「食」の時間を楽しみます。外食やテイクアウト等、バラエティーにあふれています。
「自由な生活」
※晩酌OK、夜でもお出かけOK!!
※日帰り旅行、一泊旅行OK!!
一人ひとりの想いを大切に、取り組みを行います。
「自由な生活」は、たぶのき自慢の一つ。買い物・外出・外食等たくさんの
取り組みを見に来てほしいです。
「地域と一体」
※「町内会」に入っています。
※地域行事には積極的に参加。
地域行事の手伝いはもちろんの事、様々な行事に参加します。
市民体育会・夏祭り・秋祭り・神事・大寒禊ぎ等、入居者も地域住民の一員な
ので、一緒に地域行事を盛り上げます。
「私の願い」
これからも、一人ひとりの方が、自分の「家」と感じていただけるような「自由な暮らし」「普通の暮らし」を追求し続けます。そして、心豊かに最期まで過ごせるよう、入居者と職員が一緒に楽しみながら「生活」をしていきたいです。