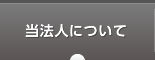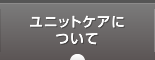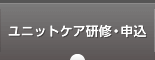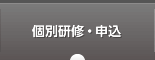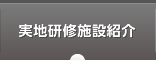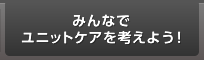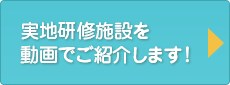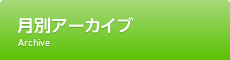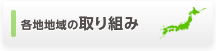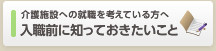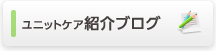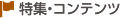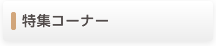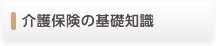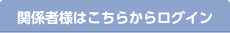特別養護老人ホームいやさか苑のユニットケアの取り組みについて(特別養護老人ホームいやさか苑 田上 優佳)
2024年6月14日 更新![]()
【理念とサービス】
いやさか苑の理念は「私たちは、「誠意」、「清潔」、「安全」の心を持って行動し、地域の方々の尊厳を支え「ゆとりと笑顔のある暮らし」を実現するため貢献します。」です。私たちは、入居者の方々の自分らしい暮らしができるよう、心地よい環境作りに努めています。
施設では、事務所スタッフによる地域の方々からの相談から、介護スタッフによる入居者への食事・入浴・排泄・移動など日常生活のお手伝い、医務スタッフによるフォローまで、幅広いサービスで支援しています。また、地域の方々による入居者の書道や折り紙クラブ、レクリエーションなどの支援を受けています。地域の大学からボランティアの活動施設にもなっています。
【施設の特徴】
いやさか苑は、ユニット内だけではなく入居者がくつろぎ心地よさを感じることができるよう花壇や玄関には季節感を感じるスペースなどの工夫をしています。落ち着いた雰囲気の中で、穏やかな時間を過ごして頂きたいと思っています。
また働く職員については、ワークライフバランスに着目した124日の休日数や有休消化率85%以上など働きやすさを重要視しています。そして、利用者主体に導入している移動移乗福祉用具を活用するムーブエイドケアや職員の腰痛対策としてのノーリフティングケアなどを展開しています。
【入居者の声】
いやさか苑での生活について、一部の入居者からは以下のような声が寄せられています。
・「明るくて良い所やね」・「職員の方が優しくて、ようしてくれます」
・「ここのご飯美味しいわ」
・「私の妻を一人の人間として大切にしてくれました」
特別養護老人ホームいやさか苑は、地域の方々にとって、いやさか苑が優しさや安心感がある場所であることを私たちは心から願っています。ぜひ一度、いやさか苑への見学や相談にお越しください。お待ちしております。

関わる全ての人のその先を見据えて、共に歩んでいこう(特別養護老人ホームりんごの丘 𠮷尾 幸治)
2024年6月14日 更新![]()
はじめまして、今年度より実地研修施設になりました福岡県福岡市にある特別養護老人ホームりんごの丘です、宜しくお願いします。
りんごの丘は、平成28年5月に開設しました。開設当初より実地研修施設を目標に取り組んできましたが、その過程の中でいろいろなことがありました。りんごの丘で働く職員はさまざまです。初めて福祉で働く人、他施設から来た人、思いや価値観も違います。そうした中でユニットケアを実践していくためには理念が大切だと痛感しました。理念を共有することで、何を大切にするべきなのか、そのためにはどういうケアが求められるのか、時間は長く経ちましたが、取り組んでいった結果、今回実地研修施設になることができました。
りんごの丘の入居者の中には、100歳近い方もいますし、若い方では70代の方もいます。高齢者だから一緒というわけではなく親子ぐらい歳の離れた方でも一緒に生活しています。それは時代背景の違いにも表れます。介護をするということは単にお世話係ではなく、その人を知ることだと思います。心や想いに寄り添える大変深く素敵な仕事だと思います。今まで長い人生を歩んで来られた方々が、りんごの丘で過ごす時間を自分らしく生活できるように、職員と一緒に大切にしていきたいと思います。
ユニットケアの理念でもある、「その人らしい暮らしの継続」ができるように、今後も職員と取り組んでいきます。
7月から研修生の受け入れをさせてもらいます。ユニットリーダーをはじめ職員も初めてのことなので緊張もするかと思いますが、良い事も失敗した事も経験してきた頼もしい職員ばかりです。研修生の方が何か一つでも自施設のヒントになるきっかけになればいいと思います。まだまだ課題もありますし、介護業界全体の課題もあります。未来介護のための準備も進めながら、職員・入居者・ご家族にとって、「りんごの丘があって良かった」と思ってもらえるように日々前進していきたいと思います
 。
。
介護の未来は、日本の明るい未来(特別養護老人ホームあんのん 施設長 吉田 貴宏)
2024年5月15日 更新![]()
皆さん、こんにちは。愛知県名古屋市にあります社会福祉法人フラワー園 特別養護老人ホームあんのん施設長の吉田です。
突然ですが、皆さんは、自分の「生きる」意味を考えたことはありますか?あなたの「生きる」意味と私の「生きる」意味が違うように、おそらく、ひとが「生きる」意味は一人ひとり異なります。
当法人では【「生きる」を共につなぐ】という基本理念のもと、様々な取り組みを行っております。あくまでも法人はそれぞれの「生きる」をつなぐ存在にすぎず、主役は法人にかかわるご利用者、職員、地域住民です。
そして、特別養護老人ホームあんのんは、「住み慣れた地域で、これまでの暮らしを継続していただきたい」との想いから、平成20年に開設した入所定員20名の小規模な特別養護老人ホームです。
施設に入居をすると、これまで通りの暮らしは行えないと思われる方も多くいらっしゃいますが、特別養護老人ホームあんのんでは、入居者おひとりお一人の暮らしのリズムを【私の暮らし実現率シート】に落とし込み、施設に入居をしても「これまでの暮らし」を再現できる仕組みを設けています。
また、【私の暮らし実現率シート】は、「これまでの暮らし」の再現だけに特化したものではなく、介護の見える化、数値化をすることのできるツールです。誰が見ても、今何をすればよいのかが記載されている為、働く職員にとっては欠かすことのできないツールとなっています。
少子高齢化の加速する我が国において、「優秀な人材が良い介護を提供できる」「〇〇の施設に入居をすれば良い介護が受けられる」では、明るい介護の未来は望めません。年齢、性別、国籍を問わず、誰もが共通認識のもと、同じ介護を提供できるという再現性こそが、これからの介護の未来には必要不可欠です。
介護の未来は、日本の未来と言っても過言ではありません。ユニットケアが目指す「その人らしい暮らしの継続」を実現するために、【私の暮らし実現率シート】が明るい日本の未来の一助となれば幸いです。